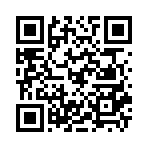2015年11月15日
ニーム図書「ニーム樹」出版

2005年にニームの不思議さを知って、ニームの素晴らしさを学習しようと考えたとき、ニーム木の原産地にインドに行くことを必然と考えました。
今年で、ニームに関わって10年が過ぎます。この間に、ニームが「農業分野」「健康分野」「環境分野」で安全に使える事実をインド政府/ニーム財団の支援・協力を得ながら、香川県を中心に検証等してきました。
今日、約1ヶ月半かけて、ニームを使ったこれらの分野でのデータ・記録等をニーム図書「ニーム樹」に記述・監修し、出版する原稿を書き上げました。
以下に、ニーム図書「ニーム樹」の目次体系を紹介します。
ニーム木に関心、興味のある方は下記のホームページにアクセスし、ご連絡ください。
目次
はじめに
第1章●ニームとは
国際連合によるニーム
アーユルヴェーダ(生命の智慧)によるニーム(1)
アーユルヴェーダ(生命の智慧)によるニーム(2)
第2章●インド政府 NGOニーム財団について
NGOニーム財団の目的
NGOニーム財団との業務提携
第3章●農業分野で利用するニーム
1.ニームケーキ%ニームペレットの作り方
2.一般的に、土の中に完熟堆肥と混ぜる「ニームペレット」と土の表層に撒く「ニームケーキ」
3.スーニーム(ニーム抽出液)の作り方
4.野菜等の苗から生育過程及び収穫まで「月と潮の動き」を見ながら、
野菜等の葉にスーニーム(ニーム抽出液)を散布する
5.農作物栽培実例
6.MSDS(製品安全データシート)
7.参考文献
第4章●健康分野で利用するニーム
1.ニーム茶
2.ニームクリーム
第5章●環境分野で利用するニーム
1.獣害被害対策
2.ニーム抽出液がしっかりと浸透したネットの設置実例
第6章●ニームを使った試験
1.オリーブ栽培(2007年~)
2.米栽培(2010年~)
3.イノシシ・シカ・たぬき・ハクビシンの行動特性(2011年~)
4.錦鯉の養殖(2012年~)
第7章●参考 小論文「A Tree For Solving Global Problems」
あとがき
<ホームページ>
http://www.humanic-info.co.jp/wordpress
2014年07月16日
農薬使用世界一の日本

農薬が過剰に使われていませんか。 - 農薬は本当に必要?
|毎年6月1日~8月31日は「農薬危害防止運動」期間です。...
生産農家さんの健全な健康があってこそ、私たち日本人は『美味しくて安全な食』が頂けます。
生産農家さんの健康管理に、消費者の私たちが「何ができるか」---「農薬危害防止運動」期間を通して考えようではありせんか。
生産農家さんは、日本の宝です。
「農薬危害防止運動」の中で
農林水産省消費・安全局長&環境省水・大気環境局長の連名で、『住宅地等における農薬使用について』文書が出されています。
以下が、最新の、『住宅地等における農薬使用について』の内容です。
住宅地等における農薬使用について
25消安第175号
環水大土発第130426号
平成25年4月26日
都道府県知事 宛
農林水産省消費・安全局長
環境省水・大気環境局長
農薬は、適正に使用されない場合、人畜及び周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。特に、学校、保育所、病院、公園等の公共施設内の植物、街路樹並びに住宅地に近接する農地(市民農園や家庭菜園を含む。)及び森林等(以下「住宅地等」という。)において農薬を使用するときは、農薬の飛散を原因とする住民、子ども等の健康被害が生じないよう、飛散防止対策の一層の徹底を図ることが必要である。
このため、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省・環境省令第5号)第6条において、「住宅の用に供する土地及びこれに近接する土地において農薬を使用するときは、農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない」と規定するとともに、「住宅地等における農薬使用について」(平成15年9月16日付け15消安第1714号農林水産省消費・安全局長通知)及び「住宅地等における農薬使用について」(平成19年1月31日付け18消安第11607号・環水大土発第070131001号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知)において、住宅地等で農薬を使用する者が遵守すべき事項を示し、関係者への指導をお願いしてきたところである。
しかしながら、依然として、(1)児童・生徒が在校中の学校や開園時間中の公園、庭園等で農薬が散布された事例、(2)街路樹等に対し害虫の発生状況にかかわらず一定の時期に決まった農薬が散布されている事例、(3)周辺住民に事前の通知がないままに農薬が散布された事例等が報告されており、地方公共団体の施設管理部局、庭園、緑地等を有する土地・施設等の管理者等に本通知の趣旨が徹底されていない場合があると考えられる。
ついては、住宅地等における農薬の適正使用を推進し、人畜への被害防止や生活環境の保全を図るため、下記の事項について貴職の協力を要請する。また、別添のとおり関係府省宛てに通知したところであり、貴管下の施設管理部局、農林部局、環境部局等の間においても緊密な連携が図られるよう配慮いただくとともに、貴管内の市区町村においても同様の取組が行われるよう、市区町村に対する周知・指導をお願いする。
なお、本通知の発出に伴い、「住宅地等における農薬使用について」(平成19年1月31日付け18消安第11607号・環水大土発第070131001号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知)は廃止する。
記
1 住宅地等における農薬使用に際しての遵守事項の指導
農薬使用者、農薬使用委託者、殺虫、殺菌、除草等の病害虫・雑草管理(以下「病害虫防除等」という。)の責任者、農薬の散布を行う土地・施設等の管理者(市民農園の開設者を含む。)(以下「農薬使用者等」という。)に対して別紙の事項を遵守するよう指導すること。
2 地方公共団体が行う病害虫防除における取組の推進
貴地方公共団体が管理する施設における植栽の病害虫防除等が、別紙の1を遵守して実施されるよう、施設管理部局及びその委託を受けて病害虫防除等を行う者に徹底すること。取組に当たっては、以下のような地方公共団体における取組事例を参考としつつ、状況に応じ効果的に行うこと。
(1)植栽管理の業務の委託に当たり、当該業務の仕様書において、農薬ラベルに表示された使用方法の遵守、周辺住民等への周知、飛散低減対策の実施、農薬の使用履歴の記帳・保管等、別紙の1に掲げる事項を業務内容として規定する。
(2)入札の資格要件として、当該業務の実施上の責任者が、当該地方公共団体が指定する研修を受けていること又は当該地方公共団体が指定する資格(農薬管理指導士、農薬適正使用アドバイザー、緑の安全管理士、技術士(農業部門・植物保護)等)を有していることを規定する。
(3)地方公共団体の施設管理部局の担当者が、本通知の周知・徹底を目的とした研修に定期的に参加する。
また、植栽管理に係る役務については、※:グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号))に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成25年2月5日変更閣議決定)において、「特定調達品目」に定められており、「住宅地等における農薬使用について」の規定に準拠して病害虫防除等が実施されることが環境物品等に該当するための要件とされている。このため、庁舎管理の担当者は、グリーン購入法の趣旨を踏まえ、委託する役務が環境物品等に該当するよう、植栽管理において本通知の遵守の徹底に努めること。
3 相談窓口の設置等の体制整備
健康被害を引き起こしかねない農薬の不適正な使用に関して周辺住民等から相談があった場合に、農林部局及び環境部局をはじめ関係部局(例えば、学校にあっては教育担当部局、街路樹にあっては道路管理担当部局)が相互に連携して対応できるよう、相談窓口を設置する等、必要な体制を整備すること。
※:グリーン購入法は、国等の公的機関が率先して環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り,持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目指しています。また、国等の各機関の取組に関することのほか、地方公共団体、事業者及び国民の責務などについても定めています。
平成12年5月に循環型社会形成推進基本法の個別法のひとつとして「国等による環境物品等の調達の推進等に
関する法律(グリーン購入法)」が制定されました。
■住宅地等における病害虫防除等に当たって遵守すべき事項
1 公園、街路樹等における病害虫防除に当たっての遵守事項
学校、保育所、病院、公園等の公共施設内の植物、街路樹及び住宅地に近接する森林等、人が居住し、滞在し、又は頻繁に訪れる土地又は施設の植栽における病害虫防除等に当たっては、次の事項を遵守すること。なお、農薬の散布を他者に委託している場合にあっては、当該土地・施設等の管理者、病害虫防除等の責任者その他の農薬使用委託者は、各事項の実施を確実なものとするため、業務委託契約等により、農薬使用者の責任を明確にするとともに、適切な研修を受講した者を作業に従事させるよう努めること。
(1)植栽の実施及び更新の際には、植栽の設置目的等を踏まえ、当該地域の自然条件に適応し、農薬 による防除を必要とする病害虫が発生しにくい植物及び品種を選定するよう努めるとともに、多様な植栽による環境の多様性確保に努めること。
(2)病害虫の発生や被害の有無にかかわらず定期的に農薬を散布することをやめ、日常的な観測によって病害虫被害 や雑草の発生を早期に発見し、被害を受けた部分のせん定や捕殺、機械除草等の物理的防除により対応するよう最大限努めること。
(3)病害虫の発生による植栽への影響や人への被害を防止するためやむを得ず農薬を使用する場合(森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)に基づき周辺の被害状況から見て松くい虫等の防除のための予防散布を行わざるを得ない場合を含む。)は、誘殺、塗布、樹幹注入等散布以外の方法を活用するとともに、やむを得ず散布する場合であっても、最小限の部位及び区域における農薬散布にとどめること。また、可能な限り、微生物農薬など人の健康への悪影響が小さいと考えられる農薬の使用の選択に努めること。
(4)農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づいて登録された、当該植物に適用のある農薬を、ラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)及び使用上の注意事項を守って使用すること。
(5)病害虫の発生前に予防的に農薬を散布しようとして、いくつかの農薬を混ぜて使用する いわゆる「現地混用」が行われている事例が見られるが、公園、街路樹等における病害虫防除では、病害虫の発生による植栽への影響や人への被害を防止するためにやむを得ず農薬を使用することが原則であり、複数の病害虫に対して同時に農薬を使用することが必要となる状況はあまり想定されないことから、このような現地混用は行わないこと。
なお、現に複数の病害虫が発生し現地混用をせざるを得ない場合であっても、『有機リン系農薬同士』の混用は、混用によって毒性影響が相加的に強まることを示唆する知見もあることから、決して行わないこと。
(6)農薬散布は、無風又は風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選び、農薬の飛散を抑制するノズル(以下「飛散低減ノズル」という。)の使用に努めるとともに、風向き、ノズルの向き等に注意して行うこと。
(7)農薬の散布に当たっては、事前に周辺住民に対して、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類及び農薬使用者等の連絡先を十分な時間的余裕をもって幅広く周知すること。その際、過去の相談等により、近辺に化学物質に敏感な人が居住していることを把握している場合には、十分配慮すること。また、農薬散布区域の近隣に学校、通学路等がある場合には、万が一にも子どもが農薬を浴びることのないよう散布の時間帯に最大限配慮するとともに、当該学校や子どもの保護者等への周知を図ること。さらに、立て看板の表示、立入制限範囲の設定等により、散布時や散布直後に、農薬使用者以外の者が散布区域内に立ち入らないよう措置すること。
(8)農薬を使用した年月日、場所及び対象植物、使用した農薬の種類又は名称並びに使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数を記録し、一定期間保管すること。病害虫防除を他者に委託している場合にあっては、当該記録の写しを農薬使用委託者が保管すること。
(9)農薬の散布後に、周辺住民等から体調不良等の相談があった場合には、農薬中毒の症状に詳しい病院又は公益財団法人日本中毒情報センターの相談窓口等を紹介すること。
(10)以上の事項の実施に当たっては、公園緑地・街路樹等における病害虫の管理に関する基本的な事項や考え方を整理した「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」(平成22年5月31日環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室)に示された技術、対策等を参考とし、状況に応じて実践すること。
2 住宅地周辺の農地における病害虫防除に当たっての遵守事項
住宅地内及び住宅地に近接した農地(市民農園や家庭菜園を含む。)において栽培される農作物の病害虫防除に当たっては、次の事項を遵守すること。
(1)病害虫に強い作物や品種の栽培、病害虫の発生しにくい適切な土づくりや施肥の実施、人手による害虫の捕殺、防虫網の設置、機械除草等の物理的防除の活用等により、農薬使用の回数及び量を削減すること。
(2)農薬を使用する場合には、農薬取締法に基づいて登録された、当該農作物に適用のある農薬を、ラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)及び使用上の注意事項を守って使用すること。
(3)粒剤、微粒剤等の飛散が少ない形状の農薬を使用するか、液体の形状で散布する農薬にあっては、飛散低減ノズルの使用に努めること。
(4)農薬散布は、無風又は風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選び、風向き、ノズルの向き等に注意して行うこと。
(5)農薬の散布に当たっては、事前に周辺住民に対して、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類及び農薬使用者等の連絡先を十分な時間的余裕をもって幅広く周知すること。その際、過去の相談等により、近辺に化学物質に敏感な人が居住していることを把握している場合には、十分配慮すること。また、農薬散布区域の近隣に学校、通学路等がある場合には、万が一にも子どもが農薬を浴びることのないよう散布の時間帯に最大限配慮するとともに、当該学校や子どもの保護者等への周知を図ること。
(6)農薬を使用した年月日、場所及び対象農作物、使用した農薬の種類又は名称並びに使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数を記録し、一定期間保管すること。
(7)農薬の散布後に、周辺住民等から体調不良等の相談があった場合には、農薬中毒の症状に詳しい病院又は公益財団法人日本中毒情報センターの相談窓口等を紹介すること。
(8)以上の事項の実施に当たっては、都道府県等の防除関係者や農業者向けの「総合的病害虫・雑草管理(IPM)実践指針」(平成17年9月30日農林水産省消費・安全局植物防疫課)や、農薬の飛散が生じるメカニズムやその低減に有効な技術をとりまとめた「農薬飛散対策技術マニュアル」(平成22年3月農林水産省消費・安全局植物防疫課)も参考とすること。
消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
担当者:農薬指導班 代表:03-3502-8111(内線4500) FAX:03-3501-3774
2010年11月07日
ミニトマト栽培
今年は、夏の気温が連日35℃を超える日が9月に入っても続き、ミニトマトの苗はこの暑さに打ち勝とうと
集中して異常なほどの花を一度にたくさん咲かせ続けました。
←(2010.11.7撮影)
この結果、花は咲けど、実がつかず、ミニトマトの茎が細くなり、ひ弱で元気がなく病気が発生した状態が今でも続いている圃場があります。
ミニトマトを植えた土壌にしっかりとたい肥を入れ「生きた土作り」に努力を重ねた農家さんの穂場は、この夏の異常な暑さで同じように花をいっぱい咲かせましたが、ミニトマトの成長点も今も元気に、勢いよく成長を続け、ミニトマトの実もしっかりつけています。
ミニトマトの収穫量は昨年の同時期に比べて少ないですが、9月の下旬から定期的な収穫が続いています。
今年のような暑さが異常に続くと、作物作りの基本が土の状態にあるのではと思わされました。
ミニトマトの栽培をしながら、次年度のたい肥作りをする努力が必要であり、たい肥の中の「エンドファイト」、すなわち、微生物の存在が必要であると思います。
自然の土の中は、好気性の微生物と嫌気性の微生物のバランスよく存在しています。
元気で健康的な人の体の中と同じです。
従来から生産農家さんは、作物の苗を植えつける前に機械的に化学農薬による土壌消毒を行い、土の中のすべての微生物(菌)を殺し、無菌状態にする作物作りを行ってきました。
今年の夏からの異常気象から、土の中に存在する好気性の微生物(菌)と嫌気性の微生物(菌)のバランスを整えた「生きた土作り」をすることが、自然界で生育する作物をどんな条件下でも元気に育てられる環境作りになるのではないかと考えさせられました。
生産農家さんの健康を第一に考えた、環境保全型の農業を進め、元気でおいしく野菜本来の香りがたっぷりの作物作りができる「生きた土作り」に挑戦して行きたいと思います。
2010年06月23日
ミニトマト栽培
今もなお、勢いよく元気に生育しています。
ミニトマトに病気や虫がいない環境が続いています。
ミニトマトの糖度も10を超えました。
甘くて昔ながらの味のミニトマトです。
6月末に、ミニトマトを撤去するのが惜しいですが、
今年8月初旬にミニトマトの植え付けをする準備に取りかかります。
今年も、十分なたい肥作りを2月から行っています。
また、今年も微生物資材(95℃以上でも生きる微生物)を入れた太陽熱消毒を行った後に、インド政府の農業プロジェクトを実施している『ニーム財団』製造の「いんど~すケーキ」に自前たい肥等を混ぜて、ミニトマトの畝作りを行い、無化学農薬・無化学肥料でミニトマトの栽培に挑戦します。
2010年06月11日
ミニトマト栽培
以下、農家さんの声-------------
ミニトマトの葉は緑が濃く、肉厚も厚く、しっかりしています。
連年だとこの時期、ミニトマトの葉は弱々しく病気にかかった葉がいっぱいあります。
今年は、ミニトマトの葉に全く病気が発生して居らず、ハウス内に害虫の発生もありません。
今なお、元気なミニトマトが生育しています。
一昨年から、圃場の土作りに力を注ぎ、有機質のたい肥を中心に、ニーム有機農業資材(インド/ニーム財団提供)及び、95℃でも生き残る微生物資材等を投入しています。
昨年の圃場の土壌消毒は、微生物資材を入れ込んだ後に太陽熱消毒を行い、土の中の有用菌を増やしながら土作りをしています。
この時期に、ミニトマトの根がしっかりしているのも、土作りの成果かと思っています。
今月末までの収穫を考えていますが、まだまだ、ミニトマトの葉の状況を見ていると収穫ができそうです。
2008年02月17日
減農薬ミニトマト栽培
< 高松市西山崎町 - 8畝 - ミニトマト ハウス栽培 >
指がスムーズに土の中に入って行くほどに、圃場の土はやわらかく、畝の表面には、白カビがたくさん発生しています。
ミニトマトの茎は太く、ミニトマトの実はぶどうの房のように付いています。
また、ミニトマトの葉の肉厚も厚く、濃い緑色をしています。
ミニトマトの味は、昔味わった自然の甘さが乗ってきており、おいしいミニトマトが食べられます。
4月上旬に茎を止めるが、次から次へと順調につぼみと花がついており、
ミニトマトの花が咲くと約45日で収穫できると言うことです。
この状況から、ミニトマトの実の大きさが均一した十分な収穫量が見込めると言うことです。
いんど~すケーキ(ニームケーキ)は、昨年8月上旬に、ミニトマトの苗の植え付け前に土壌と有機質等の肥料と混和し、畝の植えに振っています。また、10月中旬には、ミニトマトの根が伸びているところにいんど~すケーキの追肥を施しています。
いんど~すオイル(ニームオイル)は、ミニトマトが定植後から、3日~7日間隔で動噴を使って葉面散布をしています。散布後、残ったいんど~すオイルは、ミニトマトの根の周りに灌水しています。
現在の所、病気や害虫は見あたりません。昨年の秋までの温度が高かったために、1月はミニトマトの実のつきが悪かったが、今では、順調に花やつぼみがどの茎からもダブルでついており、今後の収穫が楽しみだと言うことです。