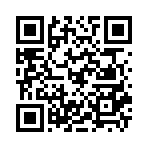2015年11月25日
2015年11月15日
ニーム図書「ニーム樹」出版

2005年にニームの不思議さを知って、ニームの素晴らしさを学習しようと考えたとき、ニーム木の原産地にインドに行くことを必然と考えました。
今年で、ニームに関わって10年が過ぎます。この間に、ニームが「農業分野」「健康分野」「環境分野」で安全に使える事実をインド政府/ニーム財団の支援・協力を得ながら、香川県を中心に検証等してきました。
今日、約1ヶ月半かけて、ニームを使ったこれらの分野でのデータ・記録等をニーム図書「ニーム樹」に記述・監修し、出版する原稿を書き上げました。
以下に、ニーム図書「ニーム樹」の目次体系を紹介します。
ニーム木に関心、興味のある方は下記のホームページにアクセスし、ご連絡ください。
目次
はじめに
第1章●ニームとは
国際連合によるニーム
アーユルヴェーダ(生命の智慧)によるニーム(1)
アーユルヴェーダ(生命の智慧)によるニーム(2)
第2章●インド政府 NGOニーム財団について
NGOニーム財団の目的
NGOニーム財団との業務提携
第3章●農業分野で利用するニーム
1.ニームケーキ%ニームペレットの作り方
2.一般的に、土の中に完熟堆肥と混ぜる「ニームペレット」と土の表層に撒く「ニームケーキ」
3.スーニーム(ニーム抽出液)の作り方
4.野菜等の苗から生育過程及び収穫まで「月と潮の動き」を見ながら、
野菜等の葉にスーニーム(ニーム抽出液)を散布する
5.農作物栽培実例
6.MSDS(製品安全データシート)
7.参考文献
第4章●健康分野で利用するニーム
1.ニーム茶
2.ニームクリーム
第5章●環境分野で利用するニーム
1.獣害被害対策
2.ニーム抽出液がしっかりと浸透したネットの設置実例
第6章●ニームを使った試験
1.オリーブ栽培(2007年~)
2.米栽培(2010年~)
3.イノシシ・シカ・たぬき・ハクビシンの行動特性(2011年~)
4.錦鯉の養殖(2012年~)
第7章●参考 小論文「A Tree For Solving Global Problems」
あとがき
<ホームページ>
http://www.humanic-info.co.jp/wordpress
2015年09月09日
ニームを使ったオリーブ穴あけゾウムシ行動試験

1. 2015年8月12日・・・小豆島からオリーブ穴あけゾウムシの成虫を6匹試験用に捕獲する。
2. 2015年8月13日・・・ペットボトルを使った試験用空間を工作する。
(1) 左の部屋(部屋の上部に空気侵入用の穴を数箇所開ける)は水を含ませたテッシュを受け皿に置く。
(2) 中古部は、左右の部屋を接続する空間、上部から空気が入るように設計する。
(3) 右の部屋(部屋の上部に空気侵入用の穴を数箇所開ける)はニームオイルを含ませたココピートを
受け皿に置く。
(4) 試験開始時は、6匹のオリーブ穴あけゾウムシの成虫をニームオイルを含ませたココピートの上に置く。
(5) ニーム葉抽出液を6匹のオリーブ穴あけゾウムシの成虫に散布する。
3. 2015年8月14日・・・試験開始1日後、1匹のオリーブ穴あけゾウムシの成虫は、左の部屋に移動。2匹のオリーブ穴あけゾウムシの
成虫は、右の部屋の受け皿のそばで仰向けになった状態で動きがない。残りの3匹は、2匹がオリーブの小枝に
1匹が右の部屋の左側に移動していた。
4. 2015年8月15日・・・試験開始2日後、右の部屋の受け皿のそばで仰向けになった状態の2匹は同じ位置で同じ状態動かない。
左の部屋に3匹、1匹は中央の接続空間に移動していた。
5. 2015年8月16日・・・試験開始3日後、右の部屋の受け皿のそばで仰向けになった状態2匹は、全く動きがなく死んだものと判断し
た。他の4匹は左の部屋のオリーブの小枝及び水がある受け皿の上に動いているものと動かないものがいた。
オリーブ穴あけゾウムシの成虫の基本行動は、夜であり、日中は死んだように動かない。
6. 2015年8月17日以降9月2日
(1) 右の部屋の受け皿のそばで仰向けになった状態の2匹は、2日目以降全く動きがなく死んでいた。
(2) 他の4匹は、中央から左の部屋を移動、右の部屋に行った動きは見られなかった。
7. 2015年9月 2日・・・試験を終了。動画を数コマ保管。
オリーブ畑での、ニームの使用方法を考えるトリガーになったと考える。
※:この試験に使ったニームは、インド政府/ニーム財団が製造した農業用資材です。
URL・・・・・http://humanic-info.co.jp/wordpress
2015年02月16日
インド訪問記ー14

一面が畑で緑に囲まれた、長閑な村ーカジュラホ駅に、約2時間遅れで到着しました。
ニューデリーを4分遅れで出発した寝台特急列車は、約3時間後にタージマハールで有名なアグラカレント駅を通過し、カジュラホ駅の一つ手前のMAHOBA駅で列車の分離があり、その後、約1時間でカジュラホ駅に到着しました。出迎えのインド人は、駅で約2時間以上、ずっと待ってくれていました。
感謝、感謝です。
インドを訪問して10年になりますが、夜の列車に一人で乗るのは初めての体験でした。
A/C 2nd Sleeping、2段ベッドの車両でしたが、車内は汚れがひどく、日本の一昔前の寝台特急列車よりもひどい感じを持ちました。
何よりも、安全にカジュラホにくることができ、ほっと、気持ちが落ち着いています。
今日の午後から、カジュラホ村に生息するニーム木を見て回り、夕方から、村の権力者とミーティングをします。
また、カジュラホ村は世界遺産に登録された寺院群があり、その一つに、「イノシシ」を神に祀った寺がある話を聞きました。
この寺院は、是非とも、見学したいと思っています。
2014年07月25日
首相が有機トマト視察

日本農業新聞(2014年7月24日)に紹介された記事です。
安倍首相が訪問した群馬県甘楽町の「甘楽町有機農業研究会」は、『土作り』にこだわったリサイクル循環型有機栽培が行われています。
ねぎ類 → 下仁田ねぎ、 長ねぎ、 赤ねぎ、 小ねぎ、 玉ねぎ、 その他
葉菜類 → 小松菜、 みぶ菜、 水菜、 べか菜、かき菜、 野沢菜
〃 白菜、 からし菜、 ター菜、 アマランサス、 ほうれん草、 レタス類
〃 エンサイ、モロヘイヤ、, ツルムラサキ、 わさび菜、 その他
果菜類 → トマト、 きゅうり、 なす、 金糸うり、 にがうり、 か ぼ ちゃ
土 物 → じゃがいも、 里芋、 にんじん、大根、 かぶ、 その他
果 樹 → キウイフルーツ
これらの農産物は、有機栽培が可能な物として選抜しています。
安倍首相は国として、『第一次産業を魅力的な産業に変えていきたい。』取り組みを進めるために、今回、有機栽培を軸とした
「甘楽町有機農業研究会」を視察地に選択しました。
香川県が県民の健康維持と生産農家さんの農産物栽培意欲向上をリンクさせるために、積極的な有機栽培への取り組み、支援等を真に実行することを期待したいと思っています。
安倍首相は、『有機栽培は技術的に難しいのではないか。』と質問をしました。
一般企業では、企業の利益と社会貢献をしながら成長を続けています。
企業は難しい局面に対峙したとき、『ピンチをチャンス』に変えて、何百年と続く会社を継続させています。
消費者が、農産物を食べた時に、『これは、本物の味で本当に美味しい、歯ごたえがある等』、直接生産農家さんの耳に感想を届けることで、生産農家さんは、安全で美味しい、生産者の健康及び自然環境を壊さない有機農業をいかにすればできるか考え、好奇心と向上心とやる気を持って、日本人のための農産物の生産に取り組む有機農業形態の輪が広げって行くと考えています。
2014年03月12日
有機のオリーブ畑に日本蜜蜂の巣箱を設置


3月6日は啓蟄の日でした。
春が近づき、虫たちが畑や果樹園の周りに出てくる季節となりました。
小豆島で、2007年から月・潮の動きを見ながら「除草剤・化学肥料・化学農薬を一切使わない-オリーブ作り」を続けています。
微生物資材、米ぬか、たい肥及びインド政府/ニーム財団が製造し、ニーム財団の試験圃場で使用している「いんど~すペレット(ニームペレット)&いんど~すバー(ニーム抽出液)」を使いながら、元気な土作りから元気なオリーブ木の生育を勧めています。
今日(3月12日)、初めての試みで、このオリーブ畑に「日本蜜蜂の巣箱」を設置しました。
蜜蜂は、害虫を攻撃する性質がある話から、蜜蜂がオリーブ畑を飛来すれば害虫が相対的に減るのではないかとの考えで試験を始めます。
今日から、5月が楽しみです。
2012年08月03日
ニームを使った米作り-6



5月27日に田植えをした稲の生育状況・稲の分けつ状況・雑草の状況<写真撮影:8月2日>
種もみの温湯消毒から、苗作り~米の収穫まで、「除草剤・化学肥料・化学農薬」を一切使わない米作りをしています。
5月27日に田植え後、
1..「いんど~すオイル」×1Lを流し込む。その直後に、「米ぬか」×45kgを撒く。
2.「魚粉」×30kgを撒く。
3.「いんど~すオイル」500倍希釈液を散布。
----- 1反当り -----
8月2日に田んぼの状況を写真に撮りました。
◎ 稲の花が咲いています。
◎ 稲の分けつ後の株が太く、固くしっかりしています。
◎ 田んぼの雑草がほとんどありません。
見事に、順調に稲の生育ができています。
あと約1ヶ月で、米の収穫になります。
米の収穫が楽しみです。
ここに紹介しました田んぼは、香川大学農学部から北東へ約2kmのところにあります。
そばに女井間池の西端から東へ約300mです。(三木町井上地区)
2012年05月26日
「ニーム」を使った米作り


2010年から始めた、米の栽培期間中は『除草剤、化学肥料、化学農薬』を一切使わない米作りは、今年で3回目となりました。
香川県高松市内の生産農家さんも毎年、徐々に増えています。
地球環境と自然循環の大切さ、米作りに田んぼの土づくりが大切、そして、農家さんの健康を害しない米作りの大切さが、少しづつ理解され、「よ~し、自然・有機栽培による米作りに挑戦しよう。」と、明確な動きの輪が広がっています。
今年初めて、参加頂いた生産農家さんが、今日(5/26)に田植えを行いました。(写真を見てください)
田んぼの入り口に、下記の案内板を掲示しました。
<有機農法/自然農法> 「いんど~すペレット」・「いんど~すオイル」を使った米栽培の流れ-参考例
◎:種もみの消毒から収穫まで、「除草剤」「化学肥料」「化学農薬」を一切使わない米作り
【1. 収穫後に、香川県農業試験場で玄米の食味値検査及びJA香川県で米の検査を実施】
【2. 収穫後に、学術的な土壌診断を実施】
米の栽培期間中は『除草剤、化学肥料、化学農薬』を一切使わない米作りで収穫した米は、消費者から注文を頂いています。
2012年03月31日
『 玄米食が危ない 』
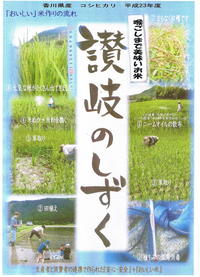
2012年、今年も米作りの季節が近づいてきました。
今年の田んぼは、生き物がどれだけいるんだろう。そして、米の収穫時に赤とんぼがどれだけ田んぼから飛び立つんだろう。
大きな希望と期待を持って、米作りの準備に入っています。
一般的に『除草剤』を使い、『化学農薬や化学肥料』を使用した慣行農法での残留農薬の場合、
その残留農薬のほとんどが米ぬかに含まれていると分析結果に出ています。
特に、玄米を食される場合に留意していただきたい内容です。
一般に、玄米の表面を覆っている『米ぬか』は、栄養価が高いことから、漬物の一種であるぬか漬けの「ぬか床(ぬかみそ)」に使用されたり、油分が多いことから油(米ぬか油)を絞ったりして、有用な部分として使用されています。
また、最近では、ぬか風呂や、ぬか加工食品もポピュラーになってきています。
★化学農薬は、疎水性の物質が多く、水に溶けにくく、油に溶け易いから、油分が多く含まれる米ぬかの部分に、残留農薬が高濃度に集積してしまいます。
さらに、これを『人間が口にした場合、人間の脂肪にも溶け込みます。』
一度体内に入ると脂肪に溶け込み、体外にはなかなか出てきません。
自然界で、体脂肪に農薬が蓄積される典型例がホッキョクグマやアザラシなどです。
また、食物連鎖を通じて濃縮されるため、彼らの脂肪を測定すると自然界にある農薬に比べて数万倍にも濃縮されて蓄積しているのです。
これが、玄米食に対して注意喚起をする理由なのです。
今年も、香川県高松で、『除草剤、化学農薬、化学肥料』を一切使わず、自然と融和した、汗を一杯かきながら米作りをします。
1.田んぼの土壌診断を大学で実施。土つくりを一生懸命にしています。
2.余剰肥料は、田んぼに投入しません。
3.植物たい肥又は動物たい肥、不足した有機質肥料、米ぬか、魚粉及びインド政府の農業プロジェクトを実行するニーム財団が使用する天然有機資材『ニーム』のみを使った米作りをします。
4.種もみの温湯消毒から、米の収穫まで、『除草剤、化学農薬、化学肥料』を一切使いません。
5.収穫後は、米の食味値及び米の検査を行います。
香川県の自然環境の中で、できる最大限の自然・有機農法で米作りを行い、この米作りの農法を県内へ広げながら、香川県の自然環境をより良くし、日本全土・世界へと共有できる農地を作って行きます。
人が豊かな地球で生活するために、地球の自然環境が循環・浄化できる生き物として存続するために、今を生きる人間がやるべきことと理解できる輪を、香川県から築き上げて行きたいと思っています。
ご賛同者とのチャッチボールをさせて頂きながら、中身がおいしい・作物(米・野菜・果物等)本来の元気を、『いただきます。』と言える食卓を作って行こうではありませんか。
2011年12月24日
ニームを使った秋野菜つくり




【写真 :左から、1・2枚・・・・・定期的に散布 / 3・4枚・・・・・散布ができていない】
ニームを使った秋野菜つくりの記録です。
有機農業資材を使った体験農園で今年初めて野菜つくりに挑戦した利用者の記録です。
【体験農園】
☆ 学術的な土壌診断を行い、必要な有機肥料を投入し、元気な土づくりをしています。
2011.7 秋野菜に植える苗の種を「いんど~すケーキ(ニームケーキ)」を混ぜた培土に蒔きました。
双葉が出た後は、1週間ごとに500倍に希釈した「いんど~すオイル(ニームオイル)」を苗に散布しました。
------ 元気な苗を作るためです -----
2011.8.下旬 秋野菜を植える土壌に、たい肥と「いんど~すペレット(ニームペレット)」をまでて畝を作りました。
2011.9.上旬 秋野菜の苗を植付しました。
植付後は、1週間に一度、500倍に希釈した「いんど~すオイル(ニームオイル)」を苗に散布してください。
『元気でおいしい野菜をつくる』話をしました。
2011.11.下旬 体験農園でびっくり。
「いんど~すオイル(ニームオイル)」を定期的に散布した野菜、特に、みごとに生育した『キャベツ』を見てびっくり。
写真を撮って記録にしました。
純度100%、インド/NGOニーム財団から提供され、※:品質と安全を保証された「いんど~すオイル(ニームオイル)」に
感謝・感謝です。
※:成分分析: SGSレポート(世界最大級の分析機関)
安全性 : 製品安全データーシート(MSDS)
◎家庭菜園・有機農業で野菜・花等を作られる方々に、有機農業資材「ニーム」をお勧めします。
2011年12月24日
ニームを使った秋野菜つくり




【写真 :左から、1・2枚・・・・・定期的に散布 / 3・4枚・・・・・散布ができていない】
ニームを使った秋野菜つくりの記録です。
有機農業資材を使った体験農園で今年初めて野菜つくりに挑戦した利用者の記録です。
【体験農園】
☆ 学術的な土壌診断を行い、必要な有機肥料を投入し、元気な土づくりをしています。
2011.7 秋野菜に植える苗の種を「いんど~すケーキ(ニームケーキ)」を混ぜた培土に蒔きました。
双葉が出た後は、1週間ごとに500倍に希釈した「いんど~すオイル(ニームオイル)」を苗に散布しました。
------ 元気な苗を作るためです -----
2011.8.下旬 秋野菜を植える土壌に、たい肥と「いんど~すペレット(ニームペレット)」をまでて畝を作りました。
2011.9.上旬 秋野菜の苗を植付しました。
植付後は、1週間に一度、500倍に希釈した「いんど~すオイル(ニームオイル)」を苗に散布してください。
『元気でおいしい野菜をつくる』話をしました。
2011.11.下旬 体験農園でびっくり。
「いんど~すオイル(ニームオイル)」を定期的に散布した野菜、特に、みごとに生育した『キャベツ』を見てびっくり。
写真を撮って記録にしました。
純度100%、インド/NGOニーム財団から提供され、※:品質と安全を保証された「いんど~すオイル(ニーpムオイル)」に
感謝・感謝です。
※:成分分析: SGSレポート(世界最大級の分析機関)
安全性 : 製品安全データーシート(MSDS)
◎家庭菜園・有機農業で野菜・花等を作られる方々に、有機農業資材「ニーム」をお勧めします。
2011年11月24日
ニームを使った米作り
2011.4月から、種もみの温湯消毒で発芽から苗つくりを始めました。
苗箱に発芽した種もみを蒔いた後、1週間間隔で「いんど~すオイル(ニームオイル)」を散布して、苗つくりをしました。
5月15,20、21日に高松市内で2か所、高知県四万十町で1か所田植えを行いました。
稲の生育中に、米ぬか・魚粉・いんど~すペレット(ニームペレット)・いんど~すオイル(ニームオイル)を使い、生産農家さんには、一生懸命に米作りでして頂きながら、草取りを約3回行って頂きました。
9月上旬から10月中旬にかけて米の収穫を行いました。
写真が、化学肥料・化学農薬・除草剤を一切使わないで作った米作りの流れです。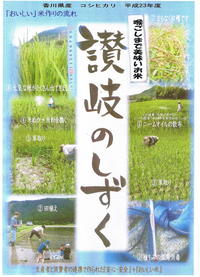
米の収穫後は、
1.米の食味値
2.米の検査
をおこないました。
米の食味値では、人がこの米を食べたときにおいしいと感じる数値結果が出ました。
この米を食べて頂いたからは、
「喉ごしまで甘くておいしいお米」と評価を頂きました。
この感想を生産農家さんに伝えると、笑顔で、
「来年も一生懸命で米を作ります。元気で米作りに大きな意欲を持ってやる気がしっかりと出てきました。」
と、言って頂き、感謝・感謝な気持ちで一杯になりました。
ありがとうございました。
来年、2012年も、生産農家さんと一緒に一生懸命に喜びの汗をかきながら米作りに励んでいきます。
苗箱に発芽した種もみを蒔いた後、1週間間隔で「いんど~すオイル(ニームオイル)」を散布して、苗つくりをしました。
5月15,20、21日に高松市内で2か所、高知県四万十町で1か所田植えを行いました。
稲の生育中に、米ぬか・魚粉・いんど~すペレット(ニームペレット)・いんど~すオイル(ニームオイル)を使い、生産農家さんには、一生懸命に米作りでして頂きながら、草取りを約3回行って頂きました。
9月上旬から10月中旬にかけて米の収穫を行いました。
写真が、化学肥料・化学農薬・除草剤を一切使わないで作った米作りの流れです。
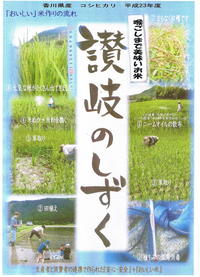
米の収穫後は、
1.米の食味値
2.米の検査
をおこないました。
米の食味値では、人がこの米を食べたときにおいしいと感じる数値結果が出ました。
この米を食べて頂いたからは、
「喉ごしまで甘くておいしいお米」と評価を頂きました。
この感想を生産農家さんに伝えると、笑顔で、
「来年も一生懸命で米を作ります。元気で米作りに大きな意欲を持ってやる気がしっかりと出てきました。」
と、言って頂き、感謝・感謝な気持ちで一杯になりました。
ありがとうございました。
来年、2012年も、生産農家さんと一緒に一生懸命に喜びの汗をかきながら米作りに励んでいきます。
2011年07月30日
2011年07月08日
【いのしし】が来た・・・ニームを使った米作り - 2011年

昨年に続いて、『ニームを使った米作り』が始まっています。
今年は、高松市で1農業法人、高知県四万十で1農業法人が加わり、3件の田んぼで行なっています。
1. 5/15田植・コシヒカリ・高松市内農業法人
2. 5/20田植・コシヒカリ・昨年始めて作った農家さん
3. 5/21田植・にこまる・四万十/仁井田郷米農業法人
『ニームを使った米作り』は、
1.もみ種の消毒・・・・・60°温度消毒(化学農薬を使わない)
2.化学肥料
3.化学農薬
を全く使わない、自然・有機栽培で行なっています。
自然環境を壊さす、農家さんの健康管理を絶対条件に、『安心・安全・おいしい』米作りを目標に、農家さんに活気ある・元気な汗を出しながら作って頂いています。
今年も、高松市内で作る『ニームを使った米』は、6月初旬に完売しました。
消費者の皆さん、ありがとうございました。
四万十の田んぼは、田植え後に数回、「いのしし」が侵入しました。
この田んぼは、山の麓にあり、車道を挟んで直下にあります。
田んぼの前方にたい肥の山があり、「いのしし」は、この中にいるミミズを食べるために、車道から一目散に田んぼを駆け抜けて行っています。
6月25日に、「いのしし」の侵入を阻止するために、田んぼの侵入経路にある車道側に、「いんど~すオイル」が入ったペットボトルを何本か吊るしました。
この日以降、この田んぼへの「いのしし」の侵入はありません。
これは、「すごいぞ。」
観察は、毎日、続けています。
2011年02月04日
「生きた土」-土作り

自然界は300年をかけて、土1ミリを作ると言われています。
「生きた土」→「生きている土」になれば雑草は生えてこない ----------- 【仮説】を立てた先生がおられます。
「生きている土」は、温かくなるだけでなく、微生物が出す粘液が土壌粒子をくっつけて団粒構造が発達します。そして、適度な湿り気と潤いのある「生きている土」になって行きます。
「生きている土」は、土壌の熱伝導率が良くなり、手で触れると温かく感じます。
実際に温度計で測ってみると、
夏の田んぼでも化学肥料や化学農薬は、土を冷やす力が強いので、どんどん地温は下がっていきます。
これに対して、有機農法/自然農法の田んぼは、化学肥料や化学農薬を使う化学農法の田んぼより、午前6時で1℃~2℃、午後3時には2℃~3℃高いことがわかっています。
自然界で作物が生育するためには、「水」+「土」が絶対条件です。
また、ヒト(人間)が成長するためには、「水」+「食物」が絶対条件になります。
大地で生きる人間は、自然環境と共生しながら生活する体構造になっていると思います。
ヒトは生きた土で作物を作り、生きた土で育ち収穫した作物を口に入れることで、継続しながら健康を作り・維持し、体の免疫力を高め、小さなケガや病気を回復させる力を身につけて行きます。
私たちが毎日、口にする作物は、私たちの継続した健康をつくる源になっています。
作物を作る農家さんや家庭菜園者さんが、土作りの大切さを体で知って、理解して頂き、有機栽培/自然栽培で作った作物を多くの人たちが食べる日本社会の輪を広げて行きたいと思っています。
2008年度、日本国内での有機農産物の割合は、
野菜・・・・・・・0.22%
米・・・・・・・・0.13% です。
有機農産物の世界市場は2000年以降、急速に成長し始めました。
日本の市場規模は、ヨーロッパ、アメリカ+カナダの市場の約20分の1です。
「生きた土」を作り、『化学農薬や化学肥料を使わない』作物作りの輪を広げて行きたい---
作物の収穫後、
1. 土壌分析を行う
2. 作物が育つ土壌pH、3要素(窒素、リン、カリ)、微量要素(塩基バランス)及び土の保肥力
(土の胃袋の大きさ)等を科学的な診断から数値で把握して行く。
従来の経験則に科学的根拠をあわせて、過度の肥料の投入をやめる。
3. 過度の肥料の投入は、作物に病気や無視の発生を助長させる原因を作る。
4. 可能な限り、完熟たい肥の投入を積み重ね、自然界に生息する山の豊かな土作りを行う。
まずは、2011年3月から、香川県初の『有機栽培による野菜作りの体験農園』を開園します。
2011年01月22日
2010年コシヒカリ有機栽培レポート

高松市内で、「コシヒカリ」を有機栽培で栽培頂いたレポ-トをインド政府の「ニーム財団」へ報告しました。
1. 栽培条件:インド/ニーム財団が製造・試験栽培に使用している「ニーム」有機農業(自然農法)資材使う。
「ニーム」有機農業(自然農法)資材は、
(1) 「いんど~すペレット」(ニームペレット) ・・・・・ 30kg/1反
(2) 「いんど~すオイル」(ニームシードオイル) ・・・・・ 約2.2L/1反
2. 「ニーム」有機農業(自然農法)資材の使用時期
(1) 「いんど~すペレット」(ニームペレット) ・・・・・・・・ 代掻きの約3-4日前
(2) 「いんど~すオイル」(ニームシードオイル) ・・・・・ 1Lは、田植えの翌日、田に水を引き込む時に同時入れる。
約0.6L×2回は、穂が出る役1週間前後に1回づつ、500倍希釈液を田の周りから田の中に向かって散布。
3. 考察:
(1) 雑草が生えづらい環境ができたと思える。
(2) 「カメムシ」による被害が抑制できたと思える。
(3) 総合的に、元気な稲作ができたと思う。
(4) 2011年は、「いんど~すペレット」(ニームペレット)を稲を植えたときに、田の中に撒いて行く。
(5) 2011年は、食味値と等級のさらなる向上を目標に、米栽培を行います。
2011年01月02日
たい肥作りから有機栽培を始めましょう
 作物を収穫した後に、「土壌分析」を必ず行い「メタボ圃場」にならない、健全で元気な「土作り」をしましょう。
作物を収穫した後に、「土壌分析」を必ず行い「メタボ圃場」にならない、健全で元気な「土作り」をしましょう。肥料投入に際して、肥料区分を熟知してください。
肥料には、「普通肥料」と「特殊肥料」があります。
「特殊肥料」の中に、「たい肥」があります。
最近、無肥料で自然栽培と言われていますが、山の土と同じ状況を畑の土作りにすることで作物を生育し収穫することを「自然栽培」と言っています。
「自然栽培」は、落ち葉や草、枯れた木の枝等をたい肥化して畑の土作りをしています。
つまり、「自然栽培」と言っても、「たい肥」が必要と言うことになります。
「たい肥」の中には微量要素を含む肥料成分があります。
人が成長するには、「水と食物」が必要であり、作物が生育するには「水と土」が必要になります。
この作物が成長する土には、「生きた土」が必要不可欠となります。
「生きた土作り」をするために、自然界では枯れた草、枯れた小枝、枯れた木や根、動物の死骸等が年月をかけて土に肥料成分を与える完熟たい肥になって行きます。
「自然栽培」で作物を作るために、「完熟たい肥」を知ることが必要になってくると思います。
完熟たい肥の腐熟の判定方法があります。
以下に、紹介します。
ご自身で「たい肥」作りをするときの参考にして頂ければ幸いです。
合計点が
30点以下は、未熟たい肥
31~80点は、中熟たい肥
81点以上は、完熟たい肥
です。 -----以下( )内は、点数です。-----
1. 色・・・・・黄-黄褐色(12)、褐色(5)、黒褐色-黒色(10)
2. 形状・・・現物の形状をとどめる(2)、かなりくずれる(5)、ほとんど認められない(10)
3. 臭気・・・ふん尿臭強い(2)、ふん尿臭弱い(5)、たい肥臭(10)
4. 水分・・・強く握ると指の間から滴る<70%以上>(2)、
強く握ると手の平にかなり付く<60%前後>(5)、
強く握っても手の平にあまり付かない<50%前後>(10)
5. たい積中の最高温度・・・・・50℃以下(2)、50-60℃(10)、60-70℃(15)、70℃以上(20)
6. たい積期間・・・・・家畜ふんだけ<20日以内>(2)、<20日-2カ月>(10)、<2カ月以上>(20)
作物収穫残さとの混合物<20日以内>(2)、<20日-3カ月>(10)、<3カ月以上>(20)
木質物との混合物<20日以内>(2)、<20日-6カ月>(10)、<6カ月以上>(20)
7. 切返し回数・・・・・2回以下(2)、3-6回(5)、7回以上(10)
8. 強制通気・・・・・・・なし(0)、あり(0)
2010年12月22日
土壌分析結果

作物を収穫した後に、必ず、土壌分析を実施することをお勧めします。
土壌分析結果から、畑の土の動きが見えてきます。
「生きた土作り」に土壌分析を活用し、野菜本来の虫や病気を跳ねのける元気な野菜作りを行いたいと思います。
【土壌分析】結果を有機栽培に活用しましょう。
1. 圃場のpHの現状と今後のpHの変動が予測できる
2. 圃場の必須元素の状況が把握できる
3. 「メタボ土壌」の予防促進ができる
4. 元肥の投入判断に利用できる
5. たい肥投入判断に利用できる
今回実施した圃場の土壌分析を写真に添付しました。
有機栽培の参考にして頂ければ幸いです。
有機栽培を行っておられる方で、
1. ご自身が使っている畑の土壌分析がしたい
2. 土壌分析に関心がある方
ご意見等、お気軽にお寄せください。
2010年12月18日
有機栽培と生きた土作り
「土作り」が、作物作りの原点であると以前にも話をしました。
そのためには、現有の土壌の状態を知っておかなければなりません。
そこで、今回初めて、この基本に基づき
今年の春から有機栽培をはじめ、野菜作りをしている畑の土壌分析を11月下旬に某大学の研究室に依頼しました。
この土壌分析結果がウェブサイトに届き、香川県農業試験場に持ち込んで、分析数値の評価やこれらの数値の活用方法・対処方法等について担当者から根拠資料を頂き学習をさせて頂きました。
土壌分析結果を効果的に次の作付けに活用するには、各々成分要素の数値の組み合わせを見ながら畑の状態を意味する動きをつかむことが重要だと考えます。
今回の土壌分析から、農家さんが土壌分析の重要さを認識し、不必要な肥料を元肥に入れないで植え付け前準備ができるようになって頂きたいと思います。
○ 明日12月19日(日)午後13:00~、
○ 仏生山の有機野菜の直売所<仏生山のマルナカ店から東へ約600m>で、
「土壌分析と生きた土作りから有機栽培に取り組む」セミナー
を行います。
有機栽培で野菜等を栽培しておられる農家さんに声をかけています。
農家さんとの間でどんな話の展開になるかが大いに楽しみにしています。
そのためには、現有の土壌の状態を知っておかなければなりません。
そこで、今回初めて、この基本に基づき
今年の春から有機栽培をはじめ、野菜作りをしている畑の土壌分析を11月下旬に某大学の研究室に依頼しました。
この土壌分析結果がウェブサイトに届き、香川県農業試験場に持ち込んで、分析数値の評価やこれらの数値の活用方法・対処方法等について担当者から根拠資料を頂き学習をさせて頂きました。
土壌分析結果を効果的に次の作付けに活用するには、各々成分要素の数値の組み合わせを見ながら畑の状態を意味する動きをつかむことが重要だと考えます。
今回の土壌分析から、農家さんが土壌分析の重要さを認識し、不必要な肥料を元肥に入れないで植え付け前準備ができるようになって頂きたいと思います。
○ 明日12月19日(日)午後13:00~、
○ 仏生山の有機野菜の直売所<仏生山のマルナカ店から東へ約600m>で、
「土壌分析と生きた土作りから有機栽培に取り組む」セミナー
を行います。
有機栽培で野菜等を栽培しておられる農家さんに声をかけています。
農家さんとの間でどんな話の展開になるかが大いに楽しみにしています。
2010年12月10日
卵かけご飯
20数年前から、山の中腹で自然環境に恵まれた所で、鶏を平飼いで、自由に運動させながら、養鶏家さん自身が有機栽培で作った野菜を混ぜた餌を食べさせて、
元気で生き生きした毎日を送る鶏から卵を頂いています。
香川県内でこのような、のびのびした環境の中で鶏を育てておられる養鶏家さんに出会え、うれしくてうれしくて、そして、この卵を分けて頂けることになり、二重の喜びを頂きました。
この卵は、仏生山に昨年10月17日にオープンした、有機栽培にこだわって作った野菜がある直売所に
置かせて頂けることになりました。
そこで、今年、有機栽培で一生懸命に育て収穫した米とのコラブレーションを考えました。
そうです。
昔懐かしい、新鮮で自然の味で頂ける『卵かけご飯』を明日(12月11日)から始めます。
10食くらい用意できます。
ぜひ、この『卵かけご飯』を食べに出かけて下さい。
有機栽培で作った米が炊き上がったときに「これぞ、米の香り」と肌に感じるご飯に、「薄黄色した黄み」が、なんとなく、ほのぼのと、昔おいしく食べた『卵かけご飯』を思い起こさせてくれると思います。
自然を感じさせてくれる食べ物が香川県にはまだまだたくさんあると思います。
楽しみが香川県にはいっぱいあります。