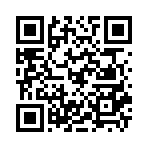2010年11月03日
健康な土作り -2
「全国農業新聞」からの抜粋---------------------------------------
土壌診断分析とその見方
3.多量要素を測定
土壌診断の中で、目に見えない土壌養分量を化学分析により測定する手段が、土壌診断分析だ。
植物は生育するために不可欠な14種類の要素を土壌から吸収する。
通常の土壌診断分析では、それらのうち多量要素と呼ばれる
(1) 窒素
(2) リン酸
(3) カリ
(4) カルシウム(石灰)
(5) マグネシウム(苦土)
を分析対象とする。
ただし、土壌中に含まれている全量でなく、作物に吸収される形態の成分のみを選び分析する。
例えば、
植物は根から有機酸を分泌し、土壌中のリン酸を溶かし吸収する。
そこで、リン酸の分析では土に希薄な硫酸を加えて溶けてきたリン酸を分析し、加給態(有効態)リン酸として表示する。
窒素(硝酸態窒素とアンモニア態窒素)・カリ・カルシウム・マグネシウムなどは土壌中でイオンとして存在する成分が根から吸収されるので、土壌を中性塩溶液で処理して、溶出するイオン形態の成分量で分析する。
分析結果は、通常「○○mg/100g」と表示されることが多いため、農家にはわかりにくい。
そこで、mg/100gの単位を「kg/10a(1反)」と読み替えると理解しやすい。
厳密には、土の密度などを考慮して換算すべきであるが、現場の土壌診断分析ではそこまで細かく考えなくても良い。
4.重要なpHとEC
土壌診断分析で養分量の測定以上に重要な項目が、pHと電気伝導率(EC)である。
土壌に一定の精製水を加え、その懸濁液のpHとECを専用の電極などで測定する。
良好な作物生育環境の目安は、
pH・・・・・6.0-6.5
EC ・・・・・0.1-0.3
である。
EC・・・・・・土壌中の硝酸態窒素量の目安となる項目である。
(1) ECの値が高い場合・・・・・窒素施用量を削減する。
(2) ハウス土壌の場合・・・・・硝酸態窒素の集積により、ECが高まり、pHga極端に低下するケースがよく見受けられる。
このような場合には、石灰資材を施用してはならない。
土の胃袋に相当する陽イオン交換容量(CEC)も重要要素の一つだが、残念ながら分析できない土壌診断室が多い。
このCECは、pHやECのように施肥管理により大きく値が変わる項目ではないので、必ずしも毎回分析するには及ばない。
CECと石灰・苦土・カリ量から土の胃袋の腫れ具合を示す塩基飽和度が算出できる。
人の健康と同じく、「腹八分目(80%)内外」がよいとされている。
5.分析に観察を加えて
この塩基飽和度や塩基バヤンスに限らず、土壌診断分析結果の数値にはあまり固執しないほうがよい。
土壌診断分析値の細かな数値にこだわり過ぎると大局を見失う恐れがあるからだ。
土壌診断分析値はファジーな目安と考えるべきで、
農家自身の「目による作物観察」と「土壌診断分析結果の数値」との併用によりその真価を発揮できる。
土壌診断分析とその見方
3.多量要素を測定
土壌診断の中で、目に見えない土壌養分量を化学分析により測定する手段が、土壌診断分析だ。
植物は生育するために不可欠な14種類の要素を土壌から吸収する。
通常の土壌診断分析では、それらのうち多量要素と呼ばれる
(1) 窒素
(2) リン酸
(3) カリ
(4) カルシウム(石灰)
(5) マグネシウム(苦土)
を分析対象とする。
ただし、土壌中に含まれている全量でなく、作物に吸収される形態の成分のみを選び分析する。
例えば、
植物は根から有機酸を分泌し、土壌中のリン酸を溶かし吸収する。
そこで、リン酸の分析では土に希薄な硫酸を加えて溶けてきたリン酸を分析し、加給態(有効態)リン酸として表示する。
窒素(硝酸態窒素とアンモニア態窒素)・カリ・カルシウム・マグネシウムなどは土壌中でイオンとして存在する成分が根から吸収されるので、土壌を中性塩溶液で処理して、溶出するイオン形態の成分量で分析する。
分析結果は、通常「○○mg/100g」と表示されることが多いため、農家にはわかりにくい。
そこで、mg/100gの単位を「kg/10a(1反)」と読み替えると理解しやすい。
厳密には、土の密度などを考慮して換算すべきであるが、現場の土壌診断分析ではそこまで細かく考えなくても良い。
4.重要なpHとEC
土壌診断分析で養分量の測定以上に重要な項目が、pHと電気伝導率(EC)である。
土壌に一定の精製水を加え、その懸濁液のpHとECを専用の電極などで測定する。
良好な作物生育環境の目安は、
pH・・・・・6.0-6.5
EC ・・・・・0.1-0.3
である。
EC・・・・・・土壌中の硝酸態窒素量の目安となる項目である。
(1) ECの値が高い場合・・・・・窒素施用量を削減する。
(2) ハウス土壌の場合・・・・・硝酸態窒素の集積により、ECが高まり、pHga極端に低下するケースがよく見受けられる。
このような場合には、石灰資材を施用してはならない。
土の胃袋に相当する陽イオン交換容量(CEC)も重要要素の一つだが、残念ながら分析できない土壌診断室が多い。
このCECは、pHやECのように施肥管理により大きく値が変わる項目ではないので、必ずしも毎回分析するには及ばない。
CECと石灰・苦土・カリ量から土の胃袋の腫れ具合を示す塩基飽和度が算出できる。
人の健康と同じく、「腹八分目(80%)内外」がよいとされている。
5.分析に観察を加えて
この塩基飽和度や塩基バヤンスに限らず、土壌診断分析結果の数値にはあまり固執しないほうがよい。
土壌診断分析値の細かな数値にこだわり過ぎると大局を見失う恐れがあるからだ。
土壌診断分析値はファジーな目安と考えるべきで、
農家自身の「目による作物観察」と「土壌診断分析結果の数値」との併用によりその真価を発揮できる。
Posted by ニーム at 15:26│Comments(0)
│有機栽培