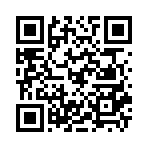2010年11月10日
「生きた土作り」に挑戦
農家さんの圃場の現状として、
1.野菜等を収穫した後に、圃場の土壌分析を行うことをほとんどしていない。
又は、土壌分析結果を反映させていない。
2.栽培する野菜等の肥料設計に書かれた肥料を栽培面積相当量、圃場に投入している。
3.圃場に残留する肥料を把握していない。
(肥料が多めに圃場に張っている場合が多く、病気や虫が来る環境を植えつけ前から作っている)
等、農家さんが管轄される部署からの机上で計算された肥料・農薬を使った野菜等の栽培が往々に多く見られます。
11月1日のNHKで放映された「環境保全型農業」の奨めは、農家さんが大いに考えさせられた内容だったと思います。
現状の「化学農薬型農業」を続けるのか、「環境保全型農業」に切り替えて野菜等を作って行くのか。
農家さんにあっては、今、まさに農業の形態を考え直す時期かもしれないと思います。
NHK放映後、
「生きた土作り」に挑戦しようと、まず、「たい肥」作りを始めました。


1.杉の木の間材をパウダー(粉状)にした主原料に、米ぬか、微生物(土壌菌)を混ぜ込んだ検体。
2.菌床栽培後の残査に、籾殻、微生物(土壌菌)を混ぜ込んだ検体。
[1] [2]
どのような「たい肥」ができるか楽しみです。
1.野菜等を収穫した後に、圃場の土壌分析を行うことをほとんどしていない。
又は、土壌分析結果を反映させていない。
2.栽培する野菜等の肥料設計に書かれた肥料を栽培面積相当量、圃場に投入している。
3.圃場に残留する肥料を把握していない。
(肥料が多めに圃場に張っている場合が多く、病気や虫が来る環境を植えつけ前から作っている)
等、農家さんが管轄される部署からの机上で計算された肥料・農薬を使った野菜等の栽培が往々に多く見られます。
11月1日のNHKで放映された「環境保全型農業」の奨めは、農家さんが大いに考えさせられた内容だったと思います。
現状の「化学農薬型農業」を続けるのか、「環境保全型農業」に切り替えて野菜等を作って行くのか。
農家さんにあっては、今、まさに農業の形態を考え直す時期かもしれないと思います。
NHK放映後、
「生きた土作り」に挑戦しようと、まず、「たい肥」作りを始めました。
1.杉の木の間材をパウダー(粉状)にした主原料に、米ぬか、微生物(土壌菌)を混ぜ込んだ検体。
2.菌床栽培後の残査に、籾殻、微生物(土壌菌)を混ぜ込んだ検体。
[1] [2]
どのような「たい肥」ができるか楽しみです。
Posted by ニーム at 23:11│Comments(0)
│有機栽培