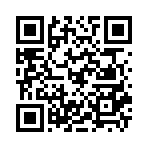2012年11月19日
ジンジャーチャイで朝食
2012年11月18日
ニーム木の下でマーケット
2012年11月18日
デリー2日目の朝
2012年11月18日
インドに到着
成田空港から約9時間30分FLT、デリーガンジー国際空港に、11月17日の早朝に到着。1年で一番気候のよい時期です。朝は、10度前後、日中の最高気温は25-27度くらいです。乾期のため、視界が悪く約1KMくらいです。ホテルの外では、通りに赤ジュータンを引き、音楽が鳴り響きながら多くの人々が集まったイベントが開かれています。
2012年10月29日
ニームを使った2012年度新米

種もみの温湯消毒から米の収穫まで、『除草剤・化学肥料・価格農薬』を一切使わないで、農家さんが汗をかきながら一生懸命に作った『2012年度こしひかり・はえぬき・ヒノヒカリ』です。
(1) 収穫後に、『米の食味値』を測定し、おいしい米の評価を頂いています。
(2) 収穫後に、JA香川県で『米の検査』を実施しています。
(3) 2013年米作りの準備で『田んぼの土の診断』を行い、元気な土作りを行っています。
自然環境に順応した米作りから、『安心・安全』で『甘くておいしい』米ができました。
玄米で安心して食べられます。米ぬかの中に化学農薬を一切含んでいません。
300g(玄米または白米)、2kg玄米または1.8kg白米で用意しています。
2012年10月03日
猪が嫌がるニーム財団使用のニーム


◎ 【インド政府の農業プロジェクトを実行するニーム財団が科学的に実証するために使うニーム】を使って、「いのしし」の動きを試験しています。
◎ 一般に国内で流通するインド等の企業が製造した『ニーム』資材ではありません。
◎ いのししは、『ニーム財団が使用するニームシードオイル』を学習した後に、『ニーム財団が使用するニームシードオイル』を嫌がる行動をしました。
1. 2012年8月の下旬にいのししが入った田んぼ
(1) 一度、いのししが入った田んぼへのいのししの侵入を100%防ぐことができていません。
(2) 周辺の田んぼの米やもち米の穂が食べられる中で、対象区の田の米の収穫はできそうです。
(3) 麻ひもにニーム財団が使用するニームシードオイルを漬け込み、対象区の田の周囲に張った時に、この麻ひもをきることがありませんでした。
2. 2012年9月17日に捕獲した「いのしし」に、『ニーム財団が使用するニームシードオイル』を使った試験
- 「ニームオイルをドブ漬けしたさつまいも」と「新鮮なさつまいも」を使う
(1) いのししは用心深く、「ニームオイルをドブ漬けしたさつまいも」に近づき、学習をした後は、このさつまいもから遠のきました。
(2) 「新鮮なさつまいも」を人の手から食べさせようとしましたが、いのししは人の手から食べません。さつまいもを柵の中へ入れるとすぐに食べます。
(3) 「ニームオイルをドブ漬けしたさつまいも」は、約3時間の試行の間、全く興味を示さず、翌朝には、柵の外に出していました。
3. 2011年にいのししが入った田に2012年、米の花が咲く前から「ニームオイルが入ったペットボトル」を吊るしたところ、この田のそばまでいのししが来たが、この田に入ることなく、今年は、米の収穫ができました。
◎ 引き続き、『ニーム財団が使用するニームシードオイル』が「いのしし」にどのように働くか学術的な試験も合わせて実証試験を継続して行きます。
2012年09月24日
ニームを使った米収穫

2012年-新米の試食・販売を行います。
1. 日時:2012年9月29日(土)及び30日(日) 12:00~18:00
2. 場所:香川県産品アンテナショップ『サンクラッケ』
<高松市南新町商店街にあります>
2012年度
種もみの温湯消毒から米の収穫まで『除草剤・化学肥料・化学農薬』を一切使わないで作った香川県産のお米です。
『安心・安全・甘くておいしい』お米が取れました。
1. 2011年の秋、米の収穫後に学術的な土壌診断をT大学で行い、元気な土づくりをしています。
---雑草はほとんど生えません---
2. 2012年、米の収穫後に、『米の食味値』を測定し、『おいしい』評価がでました。
3. 2012年、米の収穫後にJA香川県で『米の検査』を受けました。
◎ 米作りの流れは、『サンクラッケ』に設置されたモニターで見て頂けます。
2012年09月14日
『インドセミナー』高松で開催

インドビジネス連続セミナーの第1部が高松で開催されました。
インドに進出した県内企業・インドに進出を計画中の企業及びインドに関心がある人たちが誰でもが参加できるイベントでした。
従来の中国へ進出した時のビジネスが先行した行為は、インドに当てはめたくない思いを切実に考えさせられました。
なぜ、インド進出なのかの前に、一呼吸おいて、
まさに、今回のイベントのテーマにあった
『インド国をしっかりと知り・理解し、ビジネス展開について考える』フローチャートが重要だと思います。
弊社は、「ニーム」という本を熟知した時に、「ニーム」木に魅了し、こんな不思議な木がインドにあることを知り、現地/インンドへ行って、「ニーム」木を研究した教授の下で、「ニーム」木を学習したい。そして、現場で理解した「ニーム」木情報を日本国内へ正確に発信したい。
この思いで、2005年の秋に初めてインドを訪問しました。
インドを訪問して、夜のガンジー国際空港(デリー)を出てびっくり。
人と車が満員電車の中と同じように身動きが取れないくらいに、空港の出口を囲んでいました。
これは、しっかりと注意喚起しながら行動しないと、再度この空港に帰ってこれないのではないかと。
人と車の集団を出たとたんに、外套のない暗夜をひたすらホテルに向けて車で走って行くのですが、目的地のホテルに本当に行くことができるのか。運しだいだなあ。との思いがその後、何度行っても同じ思いになります。
今は、インドに行くたびに、インドの新しいことを一つ知って帰ろう。そして、インドで真に信頼できる友人を作ろう。
そうすることによって、インド国を知る媒体が忠実となり、私たちの日本と大きく違う文化・習慣・物を扱う感覚の違いが理解できることに繋がって行くと考えさせられました。
日本人の感覚でインド人と対峙すると、大きなストレスを持つことになります。
明日という言葉に、日本人であれば、今日の次の日を明日と理解していると思います。しかし、インドの人たちは将来のことも明日という言葉で表現します。
生活体系の違いから日本人の感覚で思い・言動することは、インドに限らず、全世界の人たちに共通事項として言えることでしょう。
まずは、インドに行って、インドの時間軸の流れに自身の感情が無意識で受け入れられるように整えることが大切だと思います。
インドの人(この7年間で対峙した)は、信頼関係をしっかりと構築すれば、忠実に進んで思いやりを持った言動することを体験しています。
私は、インド人は日本人にとって素晴らしいパートナーになり、有能なインド人集団の輪が常に広がっていく環境にあると思います。
次回、第2部インドビジネスセミナーは、9月20日に高松で開催されます。
インドに思いのある多くの人たちが参加されることが、高松をより元気にする原動力になると、大いに期待しています。
Posted by ニーム at
20:40
│Comments(0)
2012年08月27日
ニーム木に次々に実が・・・
2012年08月03日
ニームを使った米作り-6



5月27日に田植えをした稲の生育状況・稲の分けつ状況・雑草の状況<写真撮影:8月2日>
種もみの温湯消毒から、苗作り~米の収穫まで、「除草剤・化学肥料・化学農薬」を一切使わない米作りをしています。
5月27日に田植え後、
1..「いんど~すオイル」×1Lを流し込む。その直後に、「米ぬか」×45kgを撒く。
2.「魚粉」×30kgを撒く。
3.「いんど~すオイル」500倍希釈液を散布。
----- 1反当り -----
8月2日に田んぼの状況を写真に撮りました。
◎ 稲の花が咲いています。
◎ 稲の分けつ後の株が太く、固くしっかりしています。
◎ 田んぼの雑草がほとんどありません。
見事に、順調に稲の生育ができています。
あと約1ヶ月で、米の収穫になります。
米の収穫が楽しみです。
ここに紹介しました田んぼは、香川大学農学部から北東へ約2kmのところにあります。
そばに女井間池の西端から東へ約300mです。(三木町井上地区)
2012年07月28日
ニームがいのしし侵入予防に



1.香南アグリーム 2.東植田の田んぼに吊るしたペットボトルと田んぼの周辺(左:ペットボトルを吊るす/右:電気柵)
昨年に引き続き、今年もさつまいも畑や田んぼで「いのしし」の侵入予防に「いんど~すオイル(ニームオイル)」が使われています。
1. 香南アグリーム(高松空港の北側)
昨年に引き続き、「さつまいも畑」に「いんど~すオイル(ニームオイル)」をペットボトルに入れて約3-5m間隔で畑の周りに吊るしました。
昨年は、「いのしし」が畑の近くへ出没してきた8月の下旬にペットボトルを吊るし、11月の保育所・幼稚園児の体験収穫ができました。
今年は、「いのしし」の出没が昨年に比べ早く、梅雨明け頃、「さつまいも畑」の南東側から「いのしし」が入った跡を見つけました。そして、7月20日に、いんど~すオイルを入れたペットボトルを竹竿に吊るしました。
その後(7/26現在)、「さつまいも畑」の侵入経路の手前の畑の斜面を花崗土が出るぐらい深く掘っていますが、、「さつまいも畑」への侵入はありません。
2. 東植田の田んぼ<今年初めて試験します>
周辺の田んぼの周囲に電気柵を張っているほどに、「いのしし」の侵入で困っている集落です。
田んぼに「いのしし」の侵入予防に「いんど~すオイル(ニームオイル)」入りペットボトルを吊るして、試験をして頂ける農家さんの田んぼを紹介頂き、約5m間隔でペットボトルを吊るしました。
3. 梨畑(高瀬町)
今年、2月に梨畑の土を掘り返すほどにいのしし被害があり、早々に、ペットボトルに「いんど~すペレット(ニームペレット)」を入れて畑の周囲に吊るしました。
また、3月には、梨畑に沿ってある竹林に「いのしし」がタケノコを掘って食べた跡と「いのしし」の寝床があり、ここにも、ペットボトルに「いんど~すペレット(ニームペレット)」を入れて吊るしました。
その後、竹林と梨畑へいのししの侵入はなく、6月に梨畑の近くで「いのしし」を見かけたので、梨畑に吊るしていたペットボトルに「いんど~すオイル(ニームオイル)」を入れて、「いのしし」侵入予防をしています。
7月25日現在、「いのしし」の侵入はありません。
2012年07月02日
インドからのお客さん
2012年06月23日
ニームを使った米作り-5


今日(6/23-土)、今年の米の購入を予約頂いた皆さんと農家さんが一緒になって田植えをしました。
今回で3回目(2010年から始めました)-----
◎種もみの消毒から米の収穫まで、『スミチオン、除草剤、化学農薬及び化学肥料を』一切使わない米作りです。
◎2011年の米の収穫後に、田んぼの土壌診断をT大学で実施、土つくりを一生懸命行っています。
今回、田植えに参加頂いたご家族は、皆さん小さなお子さんを育てる若い家族でした。
また、今回は田植えに昔使っていた定規を使っての田植えを体験して頂きました。
田植えを体験するのも初めてで、皆さん、新鮮な気持ちと田植えの楽しさ、田んぼの生き物観察に大いに関心を持っていました。
皆さんと一緒に植えた稲の苗が秋に立派に生育するよう、時間があるときは、田んぼに足を運んでください。
田んぼで新しい発見があると思います。
今日、田植えに参加頂いた皆さん、ありがとうございました。
収穫を楽しみに待ってください。
2012年06月09日
ニームを使った米作り-4


ホウネンエビ&ミジンコ カブトエビ
田植え後、2週間が過ぎました。
田んぼを観察すると、いろいろな生物が元気に動いています。すべてが勉強になります。
「オタマジャクシ」や「カエル」は化学農薬を使った田んぼでも見ることはできます。
また、化学農薬の使用量が少ない田んぼで「カブトエビ」を見ることもできます。
しかし、「ホウネンエビ」「ミジンコ」は、除草剤、化学肥料、化学農薬を使った田んぼで見ることができません。
3年前から、以下の手順で米作りをしながら、一つ一つ新たな発見と学習をしながら、農家さんに楽しい米作りの輪を確実に広げています。
本当に感動があり、素晴らしいことです。
◎:種もみの消毒から収穫まで、「除草剤」「化学肥料」「化学農薬」を一切使わない米作り
【1. 収穫後に、香川県農業試験場で玄米の食味値検査及びJA香川県で米の検査を実施】
【2. 収穫後に、学術的な土壌診断を実施】
「カブトエビ」・・・雑食性で、泥とともに微小生物を食べ、また雑草の根も食べるので「草取り虫」の名もあり、
生物農薬として利用する試みもある。
「カブトエビ」がたくさんいる田んぼは、雑草が少ないことでしょう。-----除草剤を使わないで米作りができる可能性大
「ミジンコ」・・・・・・・(1)魚類飼育の際にえさとして用いられる。
(2)化学物質の生態毒性の試験のために用いられる。
「ホウネンエビ」・・・(1)田植えが終わって2-3週間位たった頃、姿を見せます。
(2)あまり暑くなり過ぎると死んでしまうようです。
(3)農薬(除草剤?)が散布される時期になると、全く見られなくなるようなので、水質にもかなり敏感ではないかと思います。
今、米を作っている田んぼは、「カブトエビ」「ホウネンエビ」そして「ミジンコ」がいっぱい群をなして動いています。
2012年05月29日
ニームを使った米作り-3


<有機農法/自然農法> 「いんど~すペレット」・「いんど~すオイル」を使った米栽培の流れ-3(種もみの温湯消毒)(発信日:2012.5.29)
◎:種もみの消毒から収穫まで、「除草剤」「化学肥料」「化学農薬」を一切使わない米作り
【1. 収穫後に、香川県農業試験場で玄米の食味値検査及びJA香川県で米の検査を実施】
【2. 収穫後に、学術的な土壌診断を実施】
種もみの消毒は、「温湯消毒」です。(写真を見てください)
(1) 60℃のお湯に10分間、種もみを漬け込みます。
(2) その後、井戸水の中に漬け込みます。
(3) 種もみが鳩胸状態になるまで、定期的に井戸水を変えて、井戸水の中に漬け込みます。
一般的に行われている、種もみの消毒は化学農薬「スミチオン」の中に漬け込みます。(写真を見てください)

(1) 24時間、「スミチオン」溶液の中に漬け込みます。
(2) その後、井戸水の中に漬け込みます。
(3) 種もみが鳩胸状態になるまで、定期的に井戸水を変えて、井戸水の中に漬け込みます。
化学農薬「スミチオン」の中に、手を入れることはできません。
一般的に恒常的に行っている米の苗作りは、初めに、しっかりと化学農薬「スミチオン」で、種もみの殺菌をします。
化学農薬「スミチオン」は、他にも、香川県では、オリーブ栽培に、毎年4月から数回、オリーブの木に散布します。
化学農薬「スミチオン」を散布した農家さんは、「この日は体に大きな負担を感じる。」と言っています。
2012年05月28日
「ニーム」を使った米作り-2


<有機農法/自然農法> 「いんど~すペレット」・「いんど~すオイル」を使った米栽培の流れ-2(発信日:2012.5.28)
◎:種もみの消毒から収穫まで、「除草剤」「化学肥料」「化学農薬」を一切使わない米作り
【1. 収穫後に、香川県農業試験場で玄米の食味値検査及びJA香川県で米の検査を実施】
【2. 収穫後に、学術的な土壌診断を実施】
5月21日・・・・・・・・・・「いんど~すペレット(ニームペレット)」を混和する
5月26日・・・・・・・・・・田植え
5月27日・・・・・・・・・・田植えの翌日です。(写真を見てください) 雑草を抑制する目的で、
(1) 「いんど~すオイル(ニームオイル)」を流し込む
(2) 「米ぬか」を撒く
→田んぼの表面に「いんど~すオイル(ニームオイル)」が一面に浮いているのが見えます。
→田んぼの表面に「米ぬか」が均一に広がっているのが見えます。
→田んぼの土の表面に「いんど~すペレット(ニームペレット)」の成分が付着しています。
これらが田んぼに雑草が生えるのを抑制します。
田んぼには一切入らない。
7月10日頃まで・・・・・田んぼの湛水管理を行う
2012年05月27日
ニーム木に新芽

2008.7.15に発芽した「ニーム」木に、待ちに待った新芽が5月25日に出てきました。
今年は、旧暦で3月が2回あり、太陽暦の5月21日が旧暦の4月1日になります。
そのために、朝夕が寒い日が最近まで続きました。
4年目の春を迎えた「ニーム」木は、今年の冬も葉をすべて取り除き、「ニーム」木の体力を温存させました。
昨年は、3年目の夏に、初めて「ニーム」の花を咲かせました。しかし、「ニーム」の実はつきませんでした。
今年は、これから「ニーム」の新葉がたくさん出てくるでしょう。
次の楽しみは、いつ、「ニーム」のつぼみが見えるかです。
2008.7月から、インドの「ニーム」文献と対比しながら、高松で「ニーム」木の観察を続けています。
2012年05月26日
「ニーム」を使った米作り


2010年から始めた、米の栽培期間中は『除草剤、化学肥料、化学農薬』を一切使わない米作りは、今年で3回目となりました。
香川県高松市内の生産農家さんも毎年、徐々に増えています。
地球環境と自然循環の大切さ、米作りに田んぼの土づくりが大切、そして、農家さんの健康を害しない米作りの大切さが、少しづつ理解され、「よ~し、自然・有機栽培による米作りに挑戦しよう。」と、明確な動きの輪が広がっています。
今年初めて、参加頂いた生産農家さんが、今日(5/26)に田植えを行いました。(写真を見てください)
田んぼの入り口に、下記の案内板を掲示しました。
<有機農法/自然農法> 「いんど~すペレット」・「いんど~すオイル」を使った米栽培の流れ-参考例
◎:種もみの消毒から収穫まで、「除草剤」「化学肥料」「化学農薬」を一切使わない米作り
【1. 収穫後に、香川県農業試験場で玄米の食味値検査及びJA香川県で米の検査を実施】
【2. 収穫後に、学術的な土壌診断を実施】
米の栽培期間中は『除草剤、化学肥料、化学農薬』を一切使わない米作りで収穫した米は、消費者から注文を頂いています。
2012年05月05日
大型犬の皮膚病&ニームクリーム


写真【4月7日】 写真【4月25日】
3月下旬に、大型犬の前足が皮膚病になり、皮膚の中の肉がでてきました。
4月7日に、ニームオイルを原料にした、日本初・国産『恵みのクリーム(ニームオイルが原料)』をこの大型犬の皮膚の傷口に塗りました。
その後、2-3日毎に、大型犬の皮膚の傷口に『恵みのクリーム(ニームオイルが原料)』を塗り続けてみました。
4月25日に、大型犬の皮膚の傷口を見ると、皮膚の回復が顕著にみられました。
(皮膚に薄皮ができ、傷口の回復が見られます。)
大型犬に、『恵みのクリーム(ニームオイルが原料)』を見せると、傷のある前足を出してくるようにもなりました。(・・・そういう風に感じます。)
アーユルヴェーダに記述がある、「皮膚病」と「ニームクリーム」の利用がこの大型犬で立証されようとしています。
大型犬の皮膚の回復が楽しみです。
2012年03月31日
『 玄米食が危ない 』
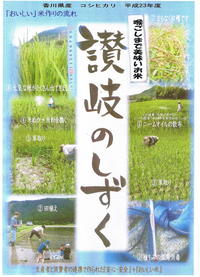
2012年、今年も米作りの季節が近づいてきました。
今年の田んぼは、生き物がどれだけいるんだろう。そして、米の収穫時に赤とんぼがどれだけ田んぼから飛び立つんだろう。
大きな希望と期待を持って、米作りの準備に入っています。
一般的に『除草剤』を使い、『化学農薬や化学肥料』を使用した慣行農法での残留農薬の場合、
その残留農薬のほとんどが米ぬかに含まれていると分析結果に出ています。
特に、玄米を食される場合に留意していただきたい内容です。
一般に、玄米の表面を覆っている『米ぬか』は、栄養価が高いことから、漬物の一種であるぬか漬けの「ぬか床(ぬかみそ)」に使用されたり、油分が多いことから油(米ぬか油)を絞ったりして、有用な部分として使用されています。
また、最近では、ぬか風呂や、ぬか加工食品もポピュラーになってきています。
★化学農薬は、疎水性の物質が多く、水に溶けにくく、油に溶け易いから、油分が多く含まれる米ぬかの部分に、残留農薬が高濃度に集積してしまいます。
さらに、これを『人間が口にした場合、人間の脂肪にも溶け込みます。』
一度体内に入ると脂肪に溶け込み、体外にはなかなか出てきません。
自然界で、体脂肪に農薬が蓄積される典型例がホッキョクグマやアザラシなどです。
また、食物連鎖を通じて濃縮されるため、彼らの脂肪を測定すると自然界にある農薬に比べて数万倍にも濃縮されて蓄積しているのです。
これが、玄米食に対して注意喚起をする理由なのです。
今年も、香川県高松で、『除草剤、化学農薬、化学肥料』を一切使わず、自然と融和した、汗を一杯かきながら米作りをします。
1.田んぼの土壌診断を大学で実施。土つくりを一生懸命にしています。
2.余剰肥料は、田んぼに投入しません。
3.植物たい肥又は動物たい肥、不足した有機質肥料、米ぬか、魚粉及びインド政府の農業プロジェクトを実行するニーム財団が使用する天然有機資材『ニーム』のみを使った米作りをします。
4.種もみの温湯消毒から、米の収穫まで、『除草剤、化学農薬、化学肥料』を一切使いません。
5.収穫後は、米の食味値及び米の検査を行います。
香川県の自然環境の中で、できる最大限の自然・有機農法で米作りを行い、この米作りの農法を県内へ広げながら、香川県の自然環境をより良くし、日本全土・世界へと共有できる農地を作って行きます。
人が豊かな地球で生活するために、地球の自然環境が循環・浄化できる生き物として存続するために、今を生きる人間がやるべきことと理解できる輪を、香川県から築き上げて行きたいと思っています。
ご賛同者とのチャッチボールをさせて頂きながら、中身がおいしい・作物(米・野菜・果物等)本来の元気を、『いただきます。』と言える食卓を作って行こうではありませんか。